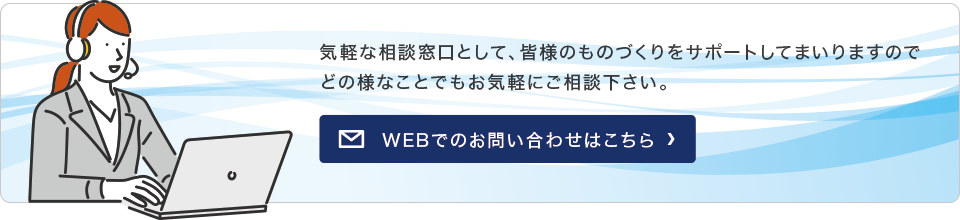ブログBlog
2025年03月10日 [アカデミック]
特許vs規格 (3) Bluetooth
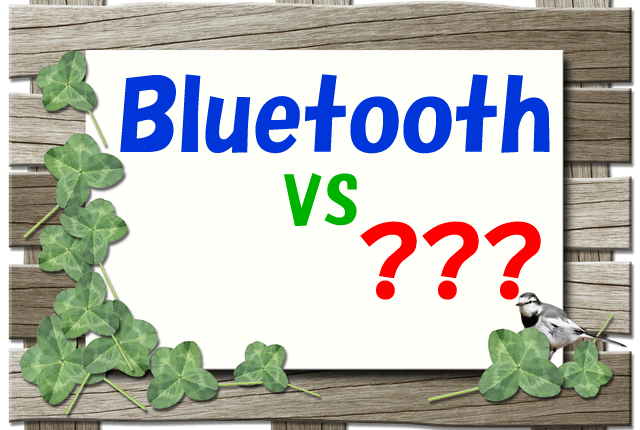 前々回、インターネット上でよく利用されるPNGフォーマットの歴史を紹介しました。
前々回、インターネット上でよく利用されるPNGフォーマットの歴史を紹介しました。前回は、ディスプレイインタフェイスのHDMIとDP(ディスプレイポート)。
その誕生の裏には、特許と行使が多く関わっていました。
今回は、第3回として短距離無線規格について紹介していきます。
今回はBluetoothの規格の概要、クライアント(依頼者)の視点。開発者の視点を綴りたいと思います。
1:規格の概要
Bluetoothは、最新バージョンは6(2024年9月)で、現在最も普及しているのが5となるでしょう。
この規格は、2.4GHz帯を利用した無線接続に利用されます。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、2.4GHz帯はBluetooth以外でも利用されています。
Wi-Fiですと5GHz帯と併用。
携帯電話・スマートフォンでの通話。
それ以外にも多くの無線通信で利用されています。
これは「ISMバンド」と呼ばれる、自由に使える電波帯なのが理由です。
Bluetoothのメリットとして、複数の通信機器が同時利用しても、干渉を防ぐ仕組みが確立されていること。
流石に電子レンジの近くなどでは特性を発揮しづらいですが、Wi-Fiに比べると通信の確保には優れていると思います。
また2010年ごろ、同じく無線規格の「Wibree (ワイブリー)」を新規格として組込み、省電力モード(BLE:Bluetooth Low Energy)の実現も果たしました。
現在多くの機器は、BLE(省電力モード)を採用しているようです。
(組込み前の規格も、「レガシー」他という名称で残っている模様)
2:依頼者クライアントの視点
Bluetoothは、ほとんどのPC、スマートフォンに搭載されています。
よって、Bluetoothの技術を利用すれば、簡単にワイヤレス接続による遠隔操作やデータ送受信が簡単に実装。
既存の技術を利用することで、開発コストの削減。
最終的には、価格への転嫁が可能かと、思い描いていると思います。
しかし、Bluetoothを利用するには、いくつか注意点があります。
開発者の視点でみてみましょう。
3:開発者の視点
クライアントが知らないことが多いこと。
Bluetoothを利用するには、多くのライセンス料が必要となります。
・SIG(団体)に参加する必要があり、その年会費。
・製品の登録、利用手数料。
Bluetoothを利用するのは、2段階のコストが発生します。
製品の出荷台数が多ければ、登録料の分散が見込まれます。
一方で、ワンオフ機(1台しか利用しない)や小ロット生産はコスト高になる傾向があります。
ここで問題になるのは、Bluetoothが必要なのか、他で代替できるか。
を考えるのが、開発者の悩みの種であり、クライアントの説得になります。
(暴論では、有線で実現可能なケースも)
ただ、Bluetoothの利用メリットも多いので、予算や開発規模によって、選べる目を養う必要があります。
利用のメリットとして、
・スマートフォンでほぼ実装されているので、通信装置回りの開発箇所が少ない。
(ソフト屋さんの手間は変わりませんが)
・ノイズに強い規格なので、利便性が高い。
・Bluetoothの適合マークがまれば、互換性の問題は少なく、テストステージの短縮化
などが挙げられます。
コストをどの様に考え、出荷数や用途を考慮して、クライアントに提案できるのが、真のBluetoothコンサルタントといえるでしょう。
今回まで3回に分けて、特許と技術の切磋琢磨の歴史を紹介してきました。
今までの流れを見るに、Bluetoothのコスト面を考慮した新規格が登場するのも、可能性としては十分にあります。
ハードウェアの教科書は、ソフトウェアに比べると圧倒的に不足しています。
当社では大学等の実験テキスト、新人教育向けのテキストなどの相談も承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。