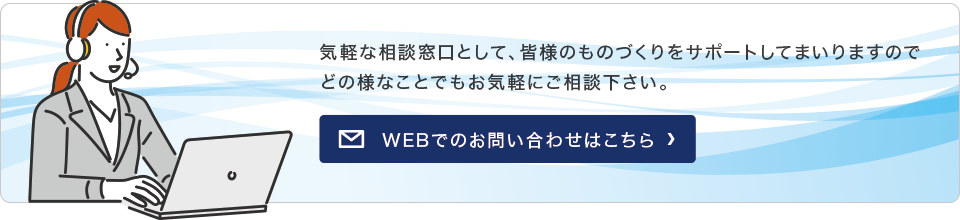ブログBlog
2025年09月01日 [アカデミック]
AIと論文執筆
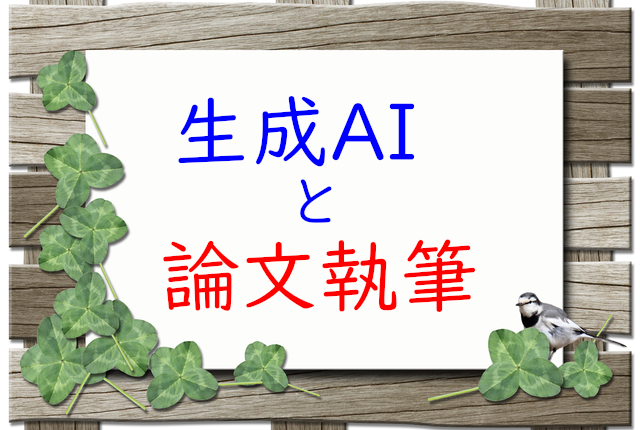 生成AIはかなり発展して、私たちの生活を豊かにしています。
生成AIはかなり発展して、私たちの生活を豊かにしています。キーワードを入力することで、画像や動画が創られることをご存じの方も多いと思います。
現在では、言語処理能力も向上し、生成AIは議事録の作成やレポートなどを半自動で生成してくれます。人間なら1時間程度かかる作業も、数分以内で原稿ができあがり、後は人間の目で確認すればOKな時代になりました。
このBlogでは、文章は拙いですが、人間味あふれる記事を執筆していきたいと思います。
(AIの進歩で、そのうち文章の上手い下手も表現できるようになるかもしれませんね)
さて、本題の「AIに論文執筆を任せて良いのか」について、考察していきたいと思います。
これは論文ではなく、レポートに多かった事例です。
みんなで作る百科事典「Wikipedia」のコピペ(コピー&ペースト:丸写し)を主軸としたレポートが多発した時期がありました。
Wikipediaの記事は玉石混交で、質の良い記事と悪い記事が存在します。もちろん、嘘や勘違いによる誤った情報も。それをベースにしたレポートは、見るに堪えないものでした。
最近では、某ゲームの情報出典を、自らが書いたWikipediaの記事を根拠にして、正しい情報だと主張。日本では、その主張に留まらず、かなりネット住民から強い反感を買っていたのは記憶に新しいと思います(2024年)。
学生レポート程度なら笑い話で済みそうですが。いずれにせよ、ネット記事をそのまま利用するのは問題となるでしょう。
これは研究者倫理に関する課題といえるでしょう。
複数の学術団体では、「論文に生成AIを使うべきではない」と声明を出していたりします。学術面からみれば正当と言えるのではないでしょうか。
生成AIが論文を制作した場合、今後その論文がAIに学習されるリスクがあります。特に初期の生成AIで作られた査読なしの論文(プレペーパー等)があったとします。後の生成AIが学習用に、この論文を取り込む可能性は十分にあります。(既にBlog記事ですら学習してしていますし)
将来的に、生成AIが自動で論文を書くようになった場合、人間の監視範囲を超えて生成AIが執筆した論文を無限増殖が起こるかもしれません。
そして、人間は生成AIを信じて・・・。
少しネガティブに考えすぎかもしれませんが、無いと言い切れない怖さがあります。
先のゲームの様に悪意のある(?)人間が作成した資料。方や実直にネット上のデータを収集して、新たなコンテンツを作り続ける生成AI。
最後は研究者がリテラシを身に着け、生成AIを始めとした技術と正しく向かい合う。AI管理者も拡張のみではない技術実装を願いたいものです。
(まだ試したことはありませんが、プログラミングができるAIがあるとか。今後に期待です)
今回は生成AIと学術論文について、記事にしました。
ハードウェアの教科書は、ソフトウェアに比べると圧倒的に不足しています。
当社では大学等の実験テキスト、新人教育向けのテキストなどの相談も承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。