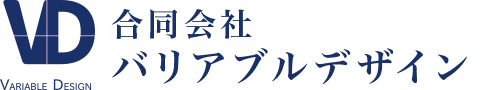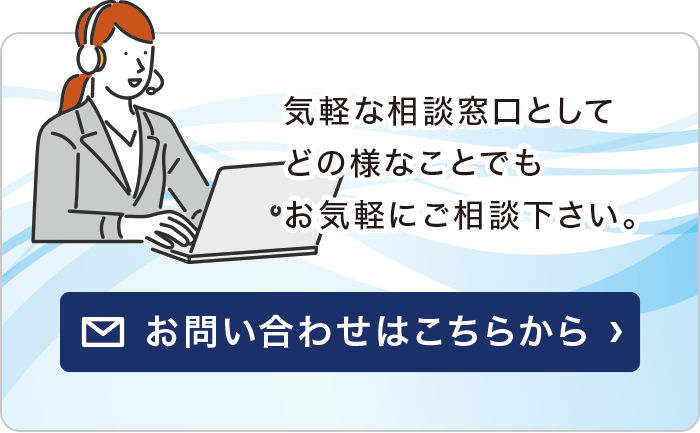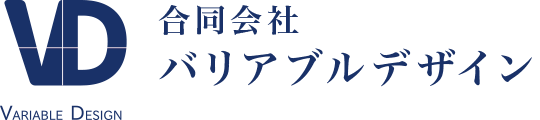[アカデミック]
2025年07月07日
七夕と学術
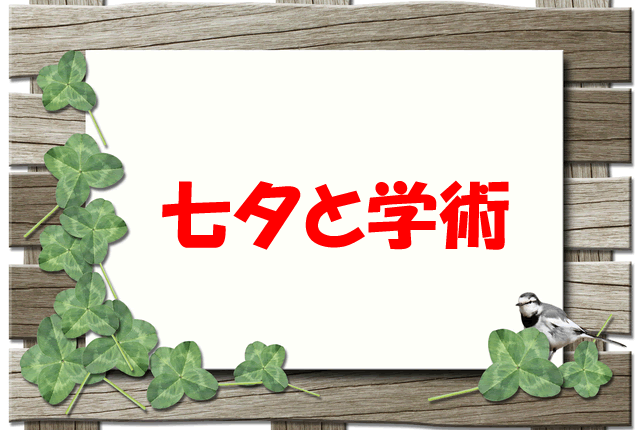 今日は7月7日の七夕です。
今日は7月7日の七夕です。
幸いにも関東は晴天で、星空を見上げることができます。
見上げることはできるのですが、町灯りが強く、等級の低い星しか見えないのが残念です。
今回は七夕を例に挙げ、そこに関連する学術を紹介していきたいと思います。
1:天文学
星や宇宙と言えば、天文学が真っ先に思い浮かぶでしょう。
天文学も分野は多岐にわたり、それぞれの専門家が日夜観察と検証を行っています。
その中で興味深いのは、時間経過による星座の歪みを挙げたいと思います。
七夕に関する星座と星は、コト座のベガ(織姫)、ワシ座アルタイル(彦星)。そしてハクチョウ座のデネブでしょうか。
天の川銀河系に属する太陽系と地球。
古来から、「天の川」と呼ばれているのは、所属している銀河系を横から見たものになります。
細かい話は省略しますが、今観察できる天体は、それぞれの銀河系や恒星となり、それぞれ独立した動きをしております。
また、地球の歳差運動(地軸のブレ)も合わさり、約8000年後にはハクチョウ座のデネブが、約1万2000後にはコト座のベガが北極星になるそうです。
歳差運動では約2万6000年で一周します。縄文人、平安人の見た星空はいかがだったか、想像が膨らみます。
(うろ覚えですが、確かNASAで、過去から未来の天体図を体験できるVRサービス存在します)
2:文化人類学
文化人類学とは、世界の様々な社会や文化を研究対象とし、人々の生活様式や価値観、社会構造などを比較・分析することで、各文化の多様性や共通性を研究する学問です。
織姫と彦星にまつわる悲話。
みなさんも、ご存じかと思います。
働き者の牽牛(牛使い)と織姫。
神様は、それぞれの褒美として二人は交際することに。
しかし、愛しすぎた故、常に想いにふけて、仕事が手つかずに。
そのことを憂いた神は、二人を離れ離れにすることを決定。
しかし、温情として年に一度の七夕の日に一日だけ会うのを許した。
この話は中国を中心に各地で似たような話が存在しています。
日本でも、古代中国風の衣装を纏っている絵が多く、それも中国から伝わった可能性も大きいでしょう。
短冊に願いを書き笹の木に吊るすのも、日本の機織りの上達を願う風習が吸収されたといわれています。
3:暦学
暦学(れきがく)とは、簡単に言えば、カレンダーに関する学問です。
その応用として、占いなどが挙げられるでしょう。
七夕は、5個ある節句の一つで、笹の節句とも呼ばれています。
他には1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句、5月5日の菖蒲の節句、9月9日の菊の節句となります。
9月9日の重陽の節句(菊の節句は別名)が最高の数字である9が並ぶ、一番尊い節句ではありますが、最近は下火に。
少し残念ではあります。
(菊=天皇家として、戦後に何かあったのかもしれませんね)
今回は趣向を変更して、七夕に関する学術の例を挙げてみました。
単に願い事を笹に結び付けて終わるのではなく、学問として頭の一部に残しておくのもいかがでしょうか?
ハードウェアの教科書は、ソフトウェアに比べると圧倒的に不足しています。
当社では大学等の実験テキスト、新人教育向けのテキストなどの相談も承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。